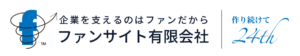昨年の暮れ、「尾形乾山と光琳」展を見に行きました。
展示会場は有楽町の「出光美術館」。
NHK日曜美術館での紹介もあり、比較的地味な企画にも関わらず大勢の、そのほとんどはシニアのご夫婦や仲間連れで、シニアのライフスタイルを考える好材料になりそうな展示会でもありました。
余談はさておいて乾山の作品を見て直感的に思ったのは、陳列台に飾られた不出世の陶工の作品はいずれもエンタテイメントとしての美の商品化ではないか、と言うことです。
まさにここにあるのは造型、色、意匠などにおいて仕掛けに充ちた美しいエンタティメントそのもの。
つまりは消費者をいかに喜ばすかに専念したクリエイターたちの美への想いとサービス精神、そしてそれをカタチにした技によるエンタティメントであり、そうした作り手の想いがそれを求め買う人々のニーズと融合して生まれた美しい楽しい売りモノたちであることです。
そしてまたこうした美しい商品は貧しい心や想像力からは決して生まれることはない、真の豊かさから創造されているという実感です。
ご承知のように尾形乾山は尾形光琳を兄とする陶工です。
そして彼らが活躍したのは元禄の時代です。
元禄時代とは狭義に解すれば,1688年9月に貞享5年から元禄と改元し,1704年3月に元禄17年が宝永と改元するまでの元禄年間をいいます。
元禄年間は悪政と世相風俗退廃の時期とする見方があると同時にそれとは逆に柳沢吉保らを中心にした貨幣経済政策がとられた時期として社会経済の発展に即応したものとする意見もありますが、いずれに与するにしろ,消費水準の向上と貨幣経済の進展という流れによる激動の時代です。
この結果、時代の主導権は武家から町衆に移行し新しい富裕層が誕生し、さらに禁欲的な価値のパラダイムが大きく変わって美を謳歌する時代だったと思われます。
こうした新しい流れに対応したのが琳派です。
琳派は桃山時代後期に興り,近代まで続いた造形芸術上の流派ですが、本阿弥光悦と俵屋宗達が創始し,尾形光琳・乾山兄弟によって発展し,酒井抱一,鈴木其一(きいつ)が江戸の地に定着させた芸術と言うのが定説です。
そして興味を引かれるのは琳派の新たな担い手として登場した尾形兄弟はその出自は雁金屋という豪商の金持ちの家柄であったことで、元禄以前の芸術の担い手であった武家や貴族、僧侶に替わっての商売人の息子たちであったことです。
言ってみれば片手にソロバン、もう一つの手には洗練された美意識をもった人材たちの登場した時代だったのです。
乾山の作品は、ほとんどが光琳とのコラボレーションから生まれたとされていますが、そのリーダーシップは乾山によるものです。
京都の仁和寺そばの鳴滝でスタートした乾山が、商売人としての面目を躍如とさせたのが二条丁字屋町へ移っての活動でしょう。
彼はいまで言う「クリエイティブマネジャー」として,粟田口や五条坂の窯を借りて懐石道具などを量産し,〈乾山焼〉とブランド化して手広く販売し,洛中の人気を集めたのです。
これは当時量産化で伊万里焼に後塵を拝してしまった京焼きの市場の再興を目的としていたと言われます。
衰退する京焼きの状況に対処して乾山が試みたことはなんだったのか?
一つは市場を伝統的な美に憧れる町衆の古典&文人趣味ニーズに絞り込んだこと。
これにより高級什器と言うニッチの市場が開発されたこと。
第二は量産化を指向しつつも小生産、限定生産により希少価値を大切にしたこと。
第三は自身がデザイナーであると同時に生産、販売を統括する経営者あったこと。
最後に自身が楽しめ、また人が楽しめる驚きを採算を度外視してすべてに試み、その成果を提供したこと。
乾山は晩年京を離れて江戸で生涯を閉じますが、彼は81歳の最後までクリエイターとして生を全うしたとのことです。
翻っていま経営にクリエイティブ思考の導入の必要が唱えられ始めました。
背景には優位性が縮小しつつある国際競争とよりよい生産性への追求が企業の生存のニーズになってきたことがあります。
その切り札として「クリエイティブ」が浮上したのです。
しかし、現実はそれへの道程はきびしいものと言わざるを得ません。
なぜならいまの経営者たちはテーラーやデミングの弟子ではあっても、T/レービットの弟子でさえもないからです。
クリエイティブ思考の導入は外部の著名デザイナーにアウトソーシングすれば事足りるほど甘くはありません。
経営にクリエイティブ思考を導入させ成功している経営者たちはファッション界を除いては、スティーブ・ジョブス、ビルゲイツその他わずかの人材が思い浮かぶだけの現実に、元禄の乾山たちの創造力を武器にした経営を想うのです。