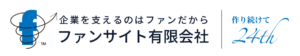5月6日、雨混じりの空模様。
その日NY53番街西11番地、改装されたニューヨーク近代美術館(MOMA)にいた。
NYラガーディア空港から、グランドセントラル駅近くのホテルにチェックインし、荷物を部屋に放り込む。
歩いてもおそらく30分ほどの距離だが、それももどかしく、ホテルの前からイエローキャブをひろう。
失敗した。
7年前とかわらない交通渋滞である。
ともかくもアップタウンへと向かう。
しばらくすると、右手に、アルパチーノが偏屈な盲目の退役軍人役を演じた佳作「セント・オブ・ウーマン」で、見事なタンゴを披露する舞台となったウォルドフ=アストリアホテルがみえる。
さらに車はパークアベニューを直進し、53番ストリートとの交差点を左折、そのまま進み5番街を横切る。
セント・トーマス教会の尖塔をみつけたらもうすぐMOMAだ。
タクシーをおり、チケット売り場へと向かう。
すでにMOMAの前には、入場を待つ列が出来ていた。
僕は大好きなクロード・モネの「睡蓮」とジャクソン・ポロックの「ワン(NO.31,1950)」が観たくてウズウズしていた。
そして、そんな気分は僕だけではないと感じた。
周囲から、なんともいえないワクワクした高揚感がたちのぼり、ざわめきとして伝わってくる。
列にならび、待つのもまた楽しい。
それにしてもなぜ、こんなにも違うのか。
比べるべくもないのだが・・・。
ここ数年、日本の美術館の多くが、入場者数を大幅に減らしている。
さらに追い討ちをかけるように、運営母体の自治体が財政難で企画展や作品購入費など軒並み予算を削減している。
公立美術館は冬の時代どころか、実態としては氷河期の状況だという。
例えば、知人のカメラマンが市民講座の講師をしていた川崎市民ミュージアムは1988年に、複製芸術作品のポスターや写 真、漫画を対象にした展示施設として開館した。
総事業費151億円、JR川崎駅からバスで40分、一番近い東横線武蔵小山駅からでもバスで20分はゆうにかかる。
開館翌年の入場者数は31万人を数えたが、次第に減少。
2002年は8万人まで激減している。
周囲は住宅地で商業施設もなく、駅からも遠く、新たな企画案もない状態が続いている。
いままさに、倒産寸前の状況であるという。
さらに、一例をあげると吉原治良や白髪一雄らを輩出した前衛芸術運動「具体美術協会」の研究と展示で広く海外でもその名が知られている芦屋市立美術博物館も、閉鎖が噂されている。
ここもまた、財政の破綻という行政の問題が横たわっている。
一方、国立近代美術館で開かれた「ゴッホ展」に出かけたが、あまりの人ごみと長蛇の列に怖じけずき、入場せずに帰ってきた。
列に並んでみてもなんだかワクワク感が無い。
いや、むしろイライラするばかりである。
なぜか?
普段、展覧会や美術展など見向きもしないくせにちょっとマスコミに取り上げられたとたん、雨後のタケノコのようにニョキニョキと集まり出て来る。
恐らく、それはゴッホの絵を観に来ているというよりも、1つのイベントととして、テレビや新聞などのキャンペーンの結果 、集まった人々に混じっている自分の所在なさに憤ったのかもしれない。
いま、日本の美術館は傾向として古今、国内外を問わず、集客力のある作家の作品を集めている。
テレビ局も新聞社も美術館を1つの事業体として位置づけている。
情けないことに、美術館側もこうしたマスコミの企画力と集客力にほぼ全面的に頼っている。
かたやMOMAは、若手作家の発掘にも熱心である。
学芸員や理事がまめに作家のアトリエに足を運び、いい作品があれば購入する。
そうして、作家を育て、美術館のコレクションとしても充実させていく。
こうした、諸外国のキューレーターにくらべ、日本の学芸員は、いずれ大学教授になりたいと望む人も多く,論文のテーマになりやすい印象派などの研究には熱心だが、新人作家を発掘してくるような努力はあまりしないとも聞く。
これでは、物故の、あるいは無名の優れた作家や作品を発見することも、育てることもできないだろうし、当の学芸員そのものが育つはずもない。
長期的なビジョンもなければ、欧米のような寄付文化もない。
こうした美術館の苦境は、今日の日本文化そのものを象徴しているのかもしれない。
高松次郎、赤瀬川源平、中西夏之、宇佐美圭司、李禹煥、関根伸夫、原口典之、高木修など、かつてキラ星のごとく登場した日本のモダンアートの作品と作家たち。
また、あのワクワクするアートシーンに出会いたい。
その願いが叶うためには革命的なアイデアも必要かもしれないが、いまは、なによりも無名の作家を発掘する目利きが必要な気がしてならない。