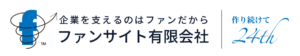なんであれ、それがどんな意味を持っているかを考える時、それがなかったらどうなるかを想像してみるというのが、手っ取り早い。
先日、百貨店の部門別売上高で化粧品が前年比1.7%のマイナスとなった。
百貨店の全商品合計の年間売上が12期連続で下がり続けている。
衣料、貴金属といった主力商品が総崩れとなるなかで、化粧品の売上はこれまで比較的好調だった。
こうした状況下での売上下落は勿論ショックであろう。
しかし、このデータは単に化粧品の売り上げ減、ということにとどまらない深刻な問題を含んでいる。
それは、化粧品の売り方にこそ百貨店の存在理由があったからだ。
これまで、口紅やマスカラなど、流行に左右され、価格勝負のメーキャップ用品はドラッグストアで購入し、化粧水やクリームなど比較的単価の高い基礎化粧品は百貨店で、との棲み分けがあった。
だから、対面で効果効能や付加価値をしっかりと時間をかけてお客様に理解してもらう。
この販売手法にこそ、コスト高の百貨店が生き残る道があった。
しかし、その棲み分けが崩れ始めたということである。
さらに、商品知識や価格比較などウェブでの購入と、それに伴う消費者のリテラシーの変化も百貨店離れに拍車をかけている。
もし、それがなくてもこまらないか?
いままさに、百貨店の存在そのものが問われはじめているのだ。