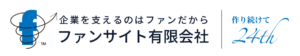「欧州の都市に比べると東京や大阪の夜は格段に明るい。
巴里などではシャンゼリゼの真ん中でもランプを燈す家があるのに、日本ではよほど辺鄙な山奥へでも行かなければそんな家は一軒もない。
恐らく世界中で電燈を贅沢に使っている国は、アメリカと日本であろう。」
1933年つまり昭和8年12月号と翌、昭和9年1月号の「経済往来」に2回わたり掲載された谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」の一節である。
数年前に訪れたことのあるローマやバルセロナにしても、そしてニューヨークでさえ、たしかに街が薄ぼんやりと暗いなという印象であったことを思い出した。
さらに「陰翳礼讃」から引用する。
「美と云うものは常に生活の実際から発達するもので、暗い部屋に住むことを餘儀なくされたわれわれの先祖は、いつしか陰翳のうちに美を発見し、やがては美のうちに目的に添うように陰翳を利用するに至った。」
漆器も屏風絵や蒔絵も女の白粉顔もすべてこの陰翳の中で、いかに美しく見せるかということの積み重ねから生まれたものであると言及している。
そして、いまから70年も前に、すでに日本の伝統文化の基本背景にある「陰翳」の世界が失われていくことをこの小説家は見抜き、嘆いていた。
学生時代、友人と京都の古寺を訪ね屏風絵を観る研修旅行をしたことがある。
いまではどこの寺でも期間限定特別公開といったキャンペーンをしているが、当時ディスカバージャパンという、とてつもなく流行った旅の広告キャンペーンで京都にも若者が押し寄せていた。
しかし、さすがにお寺の奥に仕舞い込んである古色蒼然とした屏風絵にまでは興味が及んでいなかった。
だから東京からきた画学生といえば、たいてい国宝級の屏風絵が置かれている寺の奥の院まで簡単に招き入れてもらえた。
屏風絵の前に座り、蝋燭のあかく揺れる灯りで暫くみていると、金箔があかい炎と同調し、反射し、一瞬透明な空間を作りだす。
なんと、その背景の暗闇のなかに花や木々や鳥たちが浮かんで見えてくるのである。
そうか!金は色ではなく空間を作る装置だったのかと手前勝手に合点した。
そうしてみると、入学式や卒業式、結婚式の壇上になぜか置かれている金屏風も主役である来賓や学生そして花嫁・花婿を浮かび上がらせる装置として機能しているのかな?とこれもまた勝手に了解した。
(どなたか正しい説をお分かりの方、教えてください)
明るいから様々なものがよく見えることに異論を挟む余地は無い。
しかし、暗いからこそ見えてくるものもある。
秋の夜長、部屋の灯りを少し暗くして過ごしてみるか。
月明かり
虫の音止まぬ
萩の翳(かげ)