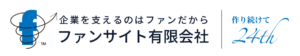人生には、遅れてやってくる人がいる。
そして、世間ではそういう人が最終的には勝ち残っているのをしばしば目にする。
間違いなく、羽原大介もその一人である。
羽原大介とは何者か。
昨年の日本映画界で、数々の賞を獲得した映画、「フラガール」の脚本家である。
さらに、一昨年は「パッチギ」をそして「ゲロッパ」とここ数年、素晴らしい活躍をみせている。
羽原は、タレントのマネージャー、大部屋付き役者、劇団員などなどを経て、劇作家つかこうへい氏のアシスタントになった。
その、つか氏のアシスタント時代、僕がかつて在籍していた会社の同僚でもあった。
つか氏のアシスタントをしながら、Vシネマや芝居の脚本を書きに書いていた。
こうして、回り道をして、ついに、映画にたどり着いた。
しかし、幸いなことに、映画の脚本こそは、もっとも遅れてやってくることを必要とするジャンルである。
勿論、若く才気溢れるものも素晴らしい。
だが、それ以上に、言葉に対する理解力、それ以上に文化的な認識、それ以上に人生経験を伴う深い共感と共鳴を映画の脚本は必要とするからだ。
当時、我々が所属していた制作会社はバブル崩壊後、本業以外の不採算部門を抱えていたことが原因で、破綻に向かっていた。
ゆえに、逃れに逃れて恵比寿から、中野新橋へと事務所を移した。
引っ越しのその日、トラック数台に分かれて作業に取りかかった。
運転手は羽原大介、そして、たまたま僕が助手席に乗り合わせた。
道行き、羽原は映画への熱く強い想いを語っていたことを思い出す。
例えば、「蒲田行進曲」の銀ちゃんとヤスとの関係のように、無骨で愚直でお人好しで、ちょっとしたたかな、でも、そんな格好わるいヤツが最後には格好良く輝く脚本が書きたい。と。
そのとき、彼こそが、つか氏の正当なる継承者になれると予感した。
いま、羽原は遅れてやってきた特権を活かし、シネマという大舞台で、思う存分に転げ回るヤスのようにも見えた。