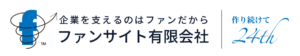夕方、5時から始まったミーティングが思いのほか早く終わった。
上手くコミュニケーションがとれているお客様とは、すべからくリズムよく進む。
しかし、ここ数日、ニ十数年来の仕事仲間との諍いがあり、出口の見つからない問題に心がザワザワにしている自分もいた。
電話で友を呼び出し、飲みに出かける気分にもなれない。
「八丁堀から神田の事務所まで歩くか。」
一人、ぶらぶらと歩き始める。
東京駅を左手奥にみながらブリヂストン本社前を通りかかる。
「そうだ、久々にモネの『睡蓮』が観たい。」
数ある東京の美術館の中でも一番好きな美術館のひとつが、八重洲にあるブリヂストン美術館である。
ここには、小ぶりではあるが一つ一つ質の高い印象派の作品が収集されている。
そして、いつ訪れても人込みに悩まされず、静寂のなかで心ゆくまで好きな作品と向かい合うことが出来る。
腕時計の針は6時を少し過ぎたばかり、たっぷり時間はある。
足はそのまま美術館へと向かう。
印象派は、それまでの絵画のテーマであった神や神話から解き放たれ、ピサロ、ルノワール、ゴーギャン、マチス、ユトリロ、ピカソ、セザンヌなど様々な才能が、彼らの心の奥底にある何かと何ものかが出会い、結びあい、新たな眼差しや色や形を獲得し、立ち現れた散文的な世界だ。
韻文の対極にある散文とは散漫な文という意味ではない。
散は型にとらわれず、制限がないということである。
型にとらわれることも無く、制限のないオリジナリティという一本勝負の世界を彼らはキャバスのうえで繰り広げていたのだ。
ぐるりと館内を回り、再び『睡蓮』の前に立つ。
『睡蓮』の絵そのものに近づいてみても、そこに睡蓮の花や葉など具体的ものはなに一つ描かれているわけではない。
ただ茫洋としたタッチと色の痕跡があるだけだ。
しかもなんの力みもなく、まるで水墨画のようにも思えるそのタッチから、なぜこれほどまでの臨場感が生まれてくるのか不思議でならない。
しばらくその絵の前に佇んでいると、なんともいえない浮遊感に襲われる。
まるで自分が水面すれすれのところに浮かび、その周りを睡蓮に囲まれているかのように感じる。
つい数十分前まで、信頼や決心の果てであったとしても、大方の事柄は始まりに比べ、終わりは空しすぎることが多いと感じていた。
それは、なにもかも欲しがる人間のくだらないプライドのせいだとも。
心のなかのザワザワとした揺れが、穏やかに静まっていく。
自分の身の丈を偽らないことから始まり、ありとあらゆることに対してすべてを率直に曝してしまう。
「率直に話をしてみよう。」
そこからしか解決の糸口は見つからない。
鏡のような水面に浮かぶ睡蓮を観ながら、明日の朝、一番に電話をしようと決めた。
——————————————————
お知らせ
取材出張のため、次回のファンサイト通信138号は3月11日配信予定です。