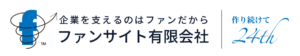事の大小に係わらず、メールで話しを済ますことが多くなり、日々、それが当たり前のようになっている。
メールで2,3度遣り取りしているうちにどうにも真意が伝わらず、往生することがある。
たとえば、「これでは困るね。」という否定的な文章でも、話しことばならトーンによってまったく違う意味を伝えることができるのに、メールではその意味の解釈を相手の気分と恣意性に委ねてしまうことになる。
どうすればそんな解読になるのかわからないまま、なにやら不穏当なことばが飛び交い、不愉快な終末を迎えることもある。
こうした事態に至った時の処方箋は一つ、直接会い、兎も角も話すことである。
相手に好感や信頼をもち話していれば、身体から発する態度やことばのトーンで、こちらの真意が伝わり、そうそうズレを生ずることはない。
だから相手の顔をみて、声を聞き、話すことである。
メールにしろ本にしろ、私たち日本人が声を発せずに文字を操るようになったのはそれほど古いことではない。
『近代読者の成立』(岩波現代文庫)の著者で、惜しまれながら逝った近代日本文学の研究者、前田愛によれば日本人が黙読を獲得したのは明治以後のことだという。
明治、大正と一般に音読の習慣はごく当たり前であったし、戦後もしばらくはそうした状況が続いていた。
そういえば、微かな記憶ではあるが、我が家に内風呂がまだなかった4,5歳のころ父に連れられ銭湯に行った。
そこでは新聞を声にだして読む老人が何人もいたことを思い出す。
新聞の連載小説を読んで聞かせる老人の回りには子供たちが群がっていた。
こうしたことは奇異な光景などではなく、ごく当たり前のこととして受け止められていた。
「太宰の文章は表面的には散文のように見えて、じつは心中で音読するうち、肉体の奥深くに潜む生理的快感を呼び覚ます詩があり、音楽であるからだ。」
長部日出雄著書『桜桃とキリスト—もうひとつの太宰治伝』を読み合点がいった。
太宰は幼いころ、母代わりの叔母に添い寝されて夜ごとに昔ばなしを聞きながら育った。
津軽弁で語られるはなしは、音律や旋律を感じさせる詩であり、音楽のようでもあったという。
こうして太宰の身体には、七五調の韻を踏む音律が刷り込まれたのではないかと長部はいう。
『富嶽百景』の書き出しも、『走れメロス』の後半部分も声に出して読むとなんとも生理的に気持ちがいい。
文章の内容の前に、ことばの持つ、音やリズムが身体に響いてくるからだ。
考えてみれば、読むことも、走ることも、食べることも、セックスすることも、仕事をすることも、身体の体験であり、生理的な喜びの記憶である。
人とことばを交わす体の芯に「好き」「嫌い」「楽しい」「悲しい」「心地よい」があるか。
メールの遣り取りに、なんの違和感も感じなくなった自分がいたら少し立ち止まることにしている。