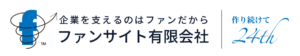春、数年ぶりに父が上京した。
歌舞伎座と六本木ヒルズに行き、「円山応挙展」を観た。
そして、そそくさと帰った。
理由は、母に任せてきた店が心配だからという。
今年82歳になる父は、いまだに現役の時計商として自営している。
仕事は出来高払いだから、出来なければ金は貰えない。
だから、休むことは仕事がないということになる。
時計を修理し、売って「なんぼ」である。
子供のころから365日、店を閉めたという記憶が僕にはない。
正月もお盆の時も、シャッターを全部は降ろさず、ふいの来客に備えていたし、一家団欒の食事の時も、お客様が来れば父か母のどちらかが席を立って店に出た。
別段そのことが不幸なことだとも思わなかったし、むしろ当たり前のこととして受け止めてきた。
業種は違うが、いま自分も自営業のような働き方をしている。
父を見ているからか、年を取ったら「働かない」とか、「働けなくなる」という感覚がピンとこない。
自営業というのは、店を閉めない限り「定年」はない。
だから「働けなくなる」ということは、例えば身体を壊したという個人的な理由であり、定年という制度的な理由によるものではない。
「年金制度が破綻の危機にある」という。
これまで、メディアでとりあげられてきた「年金の破綻」という事態は、概ね「将来とんでもない事になる可能性がある」ということの予測の先送りだったが、いまや、その事態が実態として実感できるまでになったということであろう。
その大きな要因の一つに「団塊の世代の定年」がある。
六十歳で「定年」という制度を迎え、そして世間には大量の「働かないでお金を貰う人々」が溢れる。
日本で一番人口の多い世代が、一斉に年金の受給者になるのだから、年金制度の破綻がくるのは至極当然である。
そして、国は「年金制度は破綻していない」ことを実証するため、支給額を減らし、支給開始を六十五歳にし、そのうち、七十歳にすることもありうるだろう。
ではどうするか。
「働かない人」ではなく「働けない人」を例外として、「年金をあてにする」という考え方を捨てればいい。
小賢しく年金の受給額を算出するより「年金をもらう」というこれまで当たり前だった路線から逸脱していく方法が必要ではないか。
だからこそ、いますぐにでも中高年が本気で働くことのできる社会を創造する必要がある。
それが、年金制度破綻の不安を抱えながら定年を迎え、「働かない」ことを当然のように振る舞う中高年が街に溢れ、徘徊する空恐ろしい風景を回避する唯一の方法のようにも思う。
生きて行くことと、働くことは不即不離である。