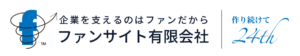東急文化村で開催されている「棟方志功展」を観て、昔のことを思い出した。
中学に入学早々、美術の授業で作った版画が公募展に入選した。
そして、公募展に入選した弘前市内の中学生と高校生の幾人かが、なぜ、どんな趣旨で集められたのかはわからないが、ともあれ1つの場所に集められた。
待つことしばらく、小柄な初老の男が会場に現れた。
牛乳瓶の底のように分厚い眼鏡をかけ、早口で、しかもひどく訛った津軽弁を話す棟方志功だった。
たしか「ねぷた」のことについて話したような記憶が微かに残っている。
その夏、棟方志功の描いた扇ねぷたが弘前の街を運行したのだから恐らく、その記憶に間違いはない。
日曜日の朝「日曜美術館」を観ていた。
97歳で永眠した熊谷守一の特集だった。
しばらく、その番組を眺めているうちに棟方志功と熊谷守一、この二人の芸術家の辿った運命はあまりに違いすぎるが、その終局は意外にも似ていることに気がついた。
棟方志功は1903年青森の鍛冶職人の6番目の子として生まれ、尋常小学校を出てから、家業を手伝っていた。
極度に視力が弱く、21歳の時に受けた徴兵検査に不合格となる。
その後、地元青森で絵の好きな仲間と絵画展などを開催するが、絵を描きたいとのおもい断ちがたく上京する。
様々な公募展に油彩画を出品するが、落選と入選を繰り返す。
そしていくつもの偶然が重なり、柳宗悦、濱田庄司、河井寛次郎ら民芸運動の中心的なメンバーに見出され、その才能が開花していくのは40 歳を過ぎてからである。
一方、熊谷守一は1880年岐阜県岐阜市の初代市長となった熊谷孫六郎の3男として生まれる。
1900年明治33年に東京芸術大学に入学、そして、西洋画家選科を首席で卒業している。
同級生には、神話や古代への憧憬を謳いあげた作品「海の幸」で浪漫主義の旗手として画壇に踊りでた青木繁がいた。
しかし、その青木はわずか28歳の若さで波乱の生涯を閉じてしまう。
そうした周囲の事柄も原因したのであろうが、熊谷はその後長らく画業から離れていた。
その有り余る才能がむしろ彼に絵を描かせなかったのかもしれない。
そして、なんと70歳を過ぎた頃から精力的に多くの作品を生み出す。
出生にも身体的にも恵まれたとは言い難い棟方と、名家に生まれ、有り余る才能に恵まれていた熊谷、この、あまりに違う生い立ちの二人のどこが似ているというのか。
棟方にはなにもなかった。
ただあるのは版画を作りたいという想いを「津軽」と「ねぶた」をベースに仏の世界で表現した。
熊谷の有り余る才能は、むしろ悩ましいばかりの拡散を生む。
そして、そうしたものから解放されるのに70歳まで待つことが必要だったのかもしれない。
こうして池袋にあった自宅の15坪ほどの庭から一歩も外に出ず、そこにある花や草や生き物たちを描いた。
自分たちの世界を限定し、その世界を見続け、その中から見えてくるものを棟方は木版に、熊谷はキャンバスに写しとったのである。
なるほど限定することは、世界を狭くすることではない。
限定し、選択し、そして集中することでエネルギーと時間は明確になる。
むしろ、豊かさはこうして生まれるのである。