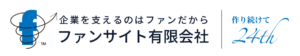東京都美術館で開催された「狩野探幽展」を観た。
探幽は徳川幕府のお抱え絵師であり、画壇の権力の頂点に立っていた人でもある。
したがって、たしかに華美で力感のこもる一種の息苦しさを感じる作品群も数多くあったが、一方で西洋絵画とはまったく異なる、余白をいかし淡白で瀟洒な水墨画には暗示と象徴が隠されているようにも思えた。
それは画家がその先になにを見ているかという世界観の違いでもあるように感じた。
私がいて、その眼差しが世界を切り取る。
西洋絵画が生み出したもっともすぐれた図法である遠近法は、画面上の全てのものの相互関係を統一的に語り、全てのものは中心点からの距離、隔たりとして描かれる。
つまり中心とは人間の代理人である画家である。
一方、山水画の世界に近代的な意味での「自然」は存在しないし、画家の眼差しも存在しない。
そこに描かれた花鳥風月、山川草木は人間の理想の世界、あるいは悟りとしての思索の場であって、花鳥風月、山川草木そのものではない。
西洋絵画の主要なモチーフとして人間ではなく自然が登場するのは17世紀と日本や中国からかなり遅れて登場する。
それは、西洋文化が「自然との隔絶あるいは対峙」するのに対し日本や中国のそれは「自然との融合」ということが根底にあるということで一般的には説明される。
しかし描かれた「自然」が何が「自然」であり何が「自然」でないかという概念が違っていればその比較は前提を失い困難なものになる。
事実、それまで四季絵とか月次(つきなみ)と呼ばれていたものが山水画と命名されたのは明治期、日本の近代化を指導したフェノロサによってであった。
本来、近代的な概念で、近代的でない文化のカタチを語ることは困難である。
だからフェノロサは西洋の物差しを持ち込み「自然との対峙」と「自然との融合」という表層の共通性の文脈のなかで文化の違いを類推できるよう西洋の規範に押し込めたのである。
繰り返すが遠近法は一つの図法でしかないにもかかわらず、個の中心性や絶対性を保障するゆえ普遍性を持ちえた。
そうやって近代は勝利をおさめてきた。
しかし、いまその絶対的自我が揺らぎ始めている。
人間は神たりえるのか、と。
ロラン・バルトは『象徴の帝国』のなかで俳句を例に、いささか法外とも受け取れるような賛辞で日本人感を述べている。
「俳句においては、ことばを惜しむことが優先的に配慮される。これは私たちヨーロッパ人には考えも及ばぬことだ。それは単に簡潔に語ることではない。そうではなくて、逆に、意味の根源そのものに触れるということなのだ。俳句は短い形式に凝縮された豊かな思想ではない。おのれにふさわしい形式を一気に見出した短い出来事なのである。」
俳句と水墨画を同一線上にならべるつもりはないが似ていなくもない。
狩野探幽の水墨画なかの風景や余白もまた論理や説明を超えた偶然や無意識という自然に自らを預けることで到達しうる世界感=モデルのことなのだろうと、ぼんやりと思った。