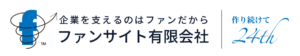多民族国家として、多様な人種と言語が混在するアメリカではその国家観形成の手段として戦争と映画という2大プロパガンダが効率よく機能している。
地域よっては英語を共通言語として使用していないエリアが数多くあり、英語をほとんど理解しないまま生活してる人々も多いと聞く。
したがって大統領の声明文はかぎりなく分かりやすく刺激的なキャッチコピーの羅列になり、映画における身体言語は喜怒哀楽の記号として機能しはじめる。
それゆえハリウッド映画の役割は国民に国家としての基本理念をやわらかく強要する道具としても十分活用される。
映画の中に描かれたヒーローとヒロインの例えば、愛。例えば勇気や友情といった倫理観や宗教観のようなものまで、あたかも普遍的な姿と行動様式として提示される。
まるで身振りと感情のカタログのように。
「パールハーバー」と「ウインドトーカーズ」で描かれた勇気と友情が、あるいは「オータムインニューヨーク」と「スィートノベンバー」で描かれた愛が・・・。
あまりの凡庸さに居眠りし、それぞれの映画が一瞬すり替えられたとしても判別できないのではないか。
ともあれ、こうして幾度となく繰り返され、描かれた愛や勇気や友情が一国の価値基準を超え、地球規模に拡大したときそれは一種の普遍的価値となり、人類全体を覆う画一的な規範にすり替わる。
そこでは、地域に根ざした固有の文化や生活様式の違いに過ぎないもの、たとえば「海洋地域での効率のよい蛋白源供給であった鯨を食べることの野蛮さ」とか「農村や遊牧社会における子供たちの手伝いが幼児労働による虐待」との烙印を押され「グローバリズムという名の正義」を押しつけられる。
悪の枢軸国と名指しされた国の1つ、イランの映画「運動靴と赤い金魚」マジット・マジディ監督(運動靴を舞台回しにした家族の愛の物語である)の冒頭のシーンは最初それがなにをしているのか判然としない。
カメラが徐々にズームアウトしていき、ようやく少女の運動靴を修理しているのだとわかる。
スニーカーを修理する生業があるということにも驚いたがその映画に映し出された彼らの生活様式、例えば家の中には靴を脱いで入る。床に座って食事をとる。廃品回収は塩と交換できる。回教徒寺院では砂糖入りの紅茶が振舞われる。など考現学的興味でも観ることができた。(本来、映画はその国々の文化の凝縮でもある)
自明のことだがイランにもイラクにも北朝鮮にも愛や勇気や友情はある。
まもなく、こんどはイラクに爆撃が開始されると聞く。
それは実のところ先進国の国益や経済システムの延命のための「正義」であることや、生産と消費を無限に膨張させ続けることが行き詰まりにきていることを知りつつ、僕たちはまた例の臭いも、痛みもないシューティングゲームのようなTVから流れる映像を見せ続けられるのだろうか。
そしてその時、僕はどちらの立場でその画面を観ているのだろうか。
映画で見慣れたアメリカ軍のパイロットの視点でか?
それとも、逃げまどうイラク市民の視点でか?