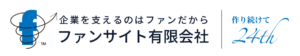あなたにとって、ものを作る原点はなにかと問われたら迷わず「熱気」であると答える。
学校を出て最初に勤めた日活撮影所には当時、梁山泊のような風情があった。
にっかつがロマンポルノ路線を始めた4年目か5年目のことである。
(71年に藤田敏八の「八月の濡れた砂」と蔵原惟二の「不良少女魔子」の一般劇場上映を最後に本編といわれる劇場用作品製作会社としての「日活」からポルノ路線の「にっかつ」に変わった)
田中登が「屋根裏の散歩者」を撮り、神代辰巳がSMの女王と呼ばれた女優の谷ナオミで「黒薔薇天昇」を撮っていた。
その年、数年ぶりの学卒採用試験で中原俊(監督作品「桜の園」)と那須博之(監督作品「ビーバップハイスクール」)2名が助監督で、和田洋(美術監督作品「GO」)やぼくも含め美術・製作助手3名の計5名が採用された。
仕事はほとんど毎日、雑用(例えば当時コンビニがなかったのでスタッフの夜食の仕込みは大変な仕事だった)とスタジオの掃除(いわゆるパシリ)であった。
破産状態であったにっかつは石原プロにTVシリーズ「西部警察」用のスタジオ(石原裕次郎は昼から食堂でビールを飲み、舘ひろしは上半身裸でバイクに跨り撮影所の中を走り回っていた記憶がなぜか鮮明に焼き付いている)をレンタルしたり、東宝(西河克己監督で「潮騒」「伊豆の踊り子」などの山口百恵と三浦友和のシリーズ)の下請けをして糊口をしのぎながら自社の映画を作っていた時期でもある。
当時直営館は3本立てであったため、黒板のスケジュール表にはいつも月、3本から3.5本ペースで撮影が組まれていた。
いま考えるととんでもない本数を作っていた。
余談だが、数は質を凌駕する!と思う。
日活ロマンポルノにはいくつかのルールがあった。
製作予算は1本2000万円以内、1時間45分で完結。
15分に1回はセックスシーンを出す。(たしかそんなことだった)
プログラムピクチャーと呼ばれる製作のフォーマットである。(最近ではTVシリーズの「私立探偵・濱マイク」などがその例)
いま考えてみると、さまざまな縛りと最低の製作環境の中でよくあれだけの作品群が生まれたものだと思う。
それでも撮影所は活気があり、熱気に満ちていた。
そして、なにより自由な雰囲気があった。
例えば、助監督や美術・製作補が集まり、空いている映写室(5つほどあった)を使い、かつて日活で製作した映画の予告編だけを集めて映写し、勉強会のようなものを開催していた。
たしか森田芳光さんと相米慎二さんが中心になり企画したものであった。(長谷川和彦、根岸吉太郎、金子修介などみんな無名の助監督時代である)
5月は熊井啓作品の予告編、6月は鈴木清順作品の予告編、7月は今村昌平作品の予告編、8月は川島雄三作品の予告編と、そんな感じで上映していた。(記憶が曖昧である。複数の監督作品がゴチャゴチャに混ざっていたのかもしれない。)
ともあれ、それまでの方法や前例が役に立たない。
しかし、前に進むしかない手探りの状態の中で、なにかを生み出そうとしていた。
一見不自由なのにむしろ自由な真空状態とでもいうような「時空」があった。
「失うものは何も無い」と思う数多くの無名の才能が鎬を削っていた。
そして、なによりも映画を作りたいという「熱気」が溢れていた。
時代は巡り今またあの「時空」が現れようとしている。
テーマや方法は違うが、再びその波が確かに押し寄せて来ている。