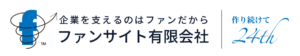四季の中でこの季節が、鳥たちの声がいちばん賑やかに感じる。
オナガ、もず、めじろ、シジュウカラ、雀・・・数も種類も結構多い。
そのさえずりに耳を傾けながら、朝の散歩は気持ちが良い。
次男が小学校に上がるのを機に、何か生き物を飼いたいと言ってきた。
そのころ、マンション住まいだったこともあり、犬や猫を飼うことは許されていなかったので金魚か、亀あたりが良いのでは、と答えた。
彼は、鳥が欲しいと言った。
横浜のデパートにあったペットショップへ出かけた。
そこで、2、3日前に生まれたばかりのオスのさくら文鳥を二羽購入した。
まだ、目も閉じたままで、くねくねと蠢くその動きは、鳥ではなく、なにが別の生き物のように感じた。
彼は毎日、砕いた餌に水を混ぜスポイトで与えた。
そして、それから餌係として朝、餌を取り替えるのが彼の日課となった。
少し身体が大きく、動きも活発な一羽は「ぴっぴ」、もう一羽を「ちっち」と名付けた。
そして、「ぴっぴ」は彼が高校1年の時、「ちっち」は高校3年まで世話をした。
さくら文鳥の平均寿命は知らないが、随分と長生きをした鳥たちだったと思う。
「ぴっぴ」は足を悪くし、鳥かごの止まり木に立つことが少なくなり、次第に巣にいることが多くなった。
ある日の朝、固くなっていた。
「ちっち」は最後まで止まり木に立ち、きれいな声でさえずっていた。
「ちっち」の最後の日にたまたま立ち会った。
止まり木から突然落ちたので、鳥かごから出してやると、大きく翼を広げバタバタと床の上を回り始めた。
その小さな躯のどこからこんなに凄い力が出ているのかと思うほどに激しく、2周、3周した後、スッと羽を閉じ、横になったまま動かなくなった。
そして、動かなくなった小さな屍を、布に包み小箱に入れ、中庭の桜の木の下に埋めた。
この二羽のさくら文鳥の死が、彼にとって初めての「家族」との別れだった。
愛おしいとは、別れることの辛さを知った時に感じる情緒のことである。
僕は褒めることの上手い親ではなかったから「ちっち」が死んだ日、彼に「よく面倒みたな。」と声を掛けることぐらいしか出来なかった。