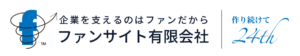ー 弟の教え ー
2001年7月12日朝、一本の電話で事態が一変しました。
弟が3年間の闘病生活の末に永眠したのです。
長男である私の代わりに家業を継ぎ、地元の商工会や、地域の祭りなども先頭に立って動いていました。
誰からも信頼されていました。
帰省したときなど、もっと活気のある町にするためにはどうしたらいいのかと夜遅くまで議論もしました。
映画が好きで、バイクにまたがり、笑顔がさまになる奴でした。
脳腫瘍。
その知らせを受け、病院に駆けつけたとき、担当医から見せられた彼の脳のCTスキャンの像が今もくっきりと目に焼きついて離れません。
脳幹の周囲に散らばる白い塊の点在、まるで宇宙に浮かぶ銀河系のような星雲にも見えました。
それが悪性腫瘍のグリオーマです。
一緒に聞いていた義妹は、その場でへたり込んでしまいました。
病院に義妹が残り、私が弟の子供たちと両親にこの事実を伝えることになりました。
病院をでると日もかげり、うっすらと肌寒く9月の津軽は、もう早くも冬の気配すら感じました。
車に乗り込み、エンジンをかけると突然、どうしようもなく嗚咽と涙を抑えることができませんでした。
元気に手を振って手術室に入って行った男が、わずか10時間後には、まったく別人のような姿になって戻って来ました。
手術のあと178センチ、110キロの巨漢が、見る影もなくやつれてしまいました。
そして、半身麻痺と視野狭窄と言語野に障害が起こりました。
もう手術はしないと決めました。
退院してからの3年間、自宅で養生していました。
家族に囲まれた時間を過ごすことが出来たことは、彼にとっても家族にとっても最高に素敵な終末だったと思っています。
私はこの間、2~3ヶ月に1度、土曜日の午後、半身麻痺になった弟を連れ出し、一緒に映画を見るために、夜行バスで定期便のように東京と故郷の弘前の間を往復しました。
金曜日夜、会社から品川へ。
22時品川発、翌朝7時15分弘前着。
土曜日の午後、一緒に映画を観る。日曜日夜10時、弘前発、翌朝月曜日、7時15分品川着。
そして、その足で、会社に出勤しました。
片道9時間の移動。
それでも、通うことを続けることができたのは、なによりも弟が一緒に映画を観ることを楽しみに待っていてくれたからです。
弟も私も映画を見ているときだけは麻痺した体のことも病気のことも忘れ、昔のように何ひとつ変わらず、ただ一緒に並んでスクリーンを眺めてられるように思えたからです。
本当にいい奴でした。
その弟の死を目の当たりにして、私の心の中で何かが音を立てて崩れ落ち、そしてこれまで先送りしていたことと向き合わなければならないことがはっきりとわかったのです。
それは、人は死ぬという事実です。
知っていることと、わかることとは違うということがわかったのです。
頭でわかっていることと、身体でわかることは違うのです。
それまで、カッコつけていました。
別に俺が主役にならなくてもいいや、それなりのポジションでそれなりにお金が稼げていればいい。
知ったかぶりを決め込み、中心的な役割をはたす人の片腕として重宝がられている自分でいい。
その気になればもっと力をだせるのに、それをしないでいる自分でいい。と。
でもそれは、主役でも脇役でもなく自己満足に浸っているだけの傍観者だったのです。
自分の人生を他人の手に委ねていたのです。
弟の死を目の当たりにして、カチッと頭の中で音がして心が決まりました。
「次の職場の当てがあるわけでもなければ、金もない。」
「もうこうなったら自分でやるしかない。」
次回につづく